離婚を考えていても、経済的な事情や子育ての都合で夫と別居できず悩んでいる方は少なくありません。特に30〜50代の女性でお子さんがいる場合、「同居したまま離婚なんてできるの?」と不安に感じることでしょう。
実際、離婚する場合に必ずしも先に別居しなければならないわけではなく、同居したまま離婚を進めるケースも少なくありません。本記事では、別居が難しい事情を抱える方向けに、同居中でも可能な離婚手続きの方法を詳しく解説します。
同居継続のメリット・デメリット、具体的な離婚手続きの流れ、子どもへの影響やお金の問題への対処法について取り上げますので、あなたの抱える疑問や不安を一つずつ解消していきましょう。
最後には無料で弁護士に相談できる方法もご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
別居できない事情と同居したままの離婚への不安
離婚したい気持ちがあっても、様々な理由で別居に踏み切れない場合があります。
例えば、経済的な理由(別居のための引っ越し費用や新居の家賃負担が難しい)、子どもの生活環境への配慮、周囲の目(世間体)の問題などで簡単に家を出られないことも多いでしょう。
同居を続けたまま離婚を検討するのは珍しいことではなく、実際に一時的な解決策として「家庭内別居」を選ぶ夫婦もいます。
しかし、同居を続けながらの離婚にはいろいろな不安がつきものです。今まさにこのページをご覧の方も、次のような疑問や悩みを抱えていないでしょうか?
- そもそも同居したまま離婚なんてできるの? 手続きを進める上で法律的に問題はないのか心配…
- 同居中に離婚手続きを進めるにはどうすればいい? 別居せず進める具体的な方法や段取りを知りたい
- 子どもに悪影響はない?親権はちゃんと取れる? 子どもの心情や親権争いへの不安がある
- お金の面は大丈夫? 財産分与や生活費の負担など金銭面で損をしないか気になる
こうした不安に寄り添いながら、本記事では同居したまま離婚する際のポイントを解説していきます。「本当に離婚できるの?」「子どもやお金はどうなる?」といった疑問に対し、一つひとつ丁寧に答えていきますので、安心して読み進めてください。
同居したまま離婚するメリット・デメリット
離婚前に別居できない事情がある場合、夫婦が同居を続けたまま離婚協議等を進めることになります。その状況にはプラス面もマイナス面もあります。まずは同居を続けながら離婚するメリット・デメリットを確認し、現状を客観的に捉えましょう。
同居を続けるメリット
同居したまま離婚に向けた話し合いを進めることには、主に次のようなメリットがあります。
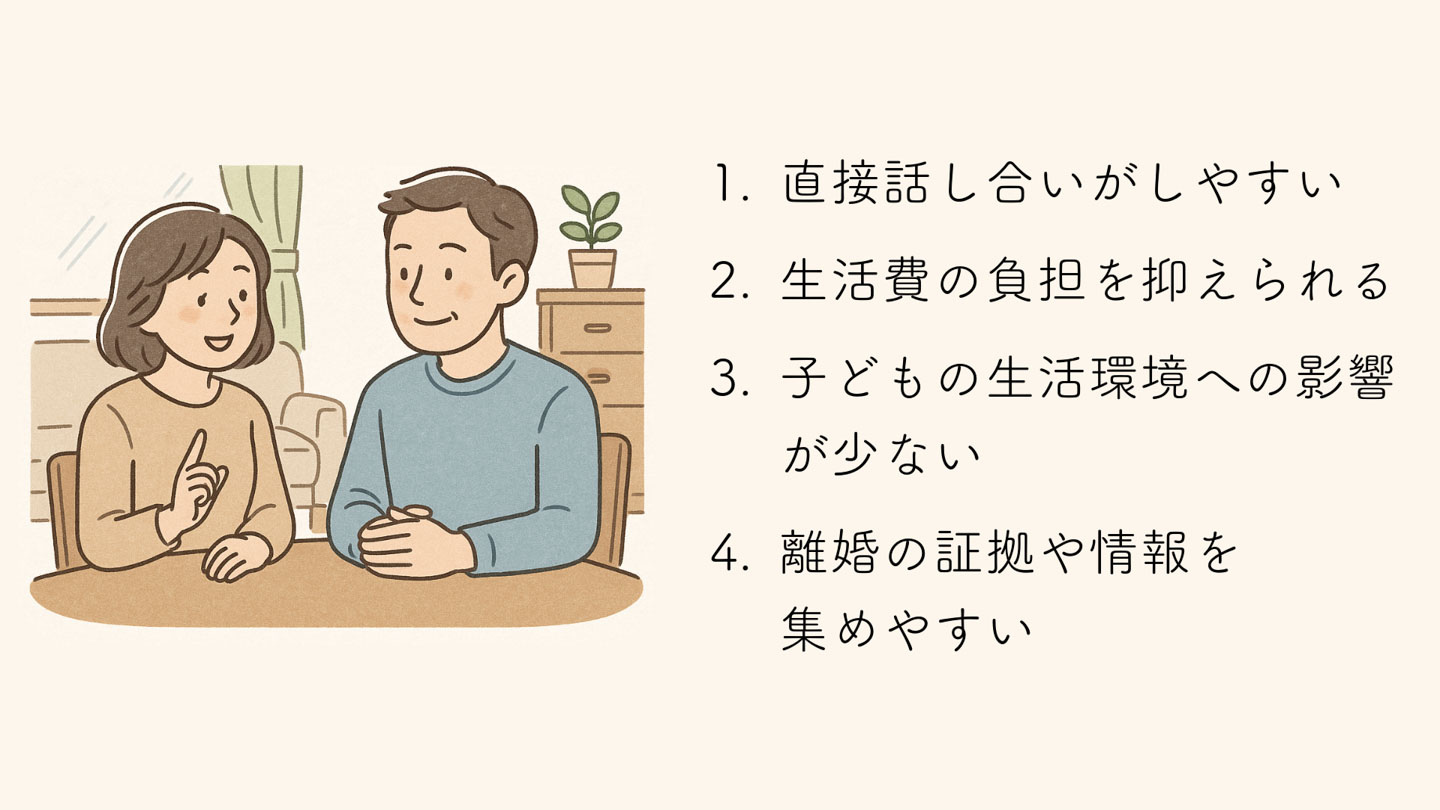
直接話し合いがしやすい
同じ家に暮らしている分、夫婦の時間が合えばいつでも顔を合わせて話し合うことが可能です。離れて暮らしていると連絡のやり取りに時間がかかりますが、同居中であれば離婚についてじっくり話し合う機会を持ちやすく、短期間で合意に至ることもあり得ます。
お互い冷静に話せる関係であれば、同居の方が協議離婚(話し合いによる離婚)を早期に成立させやすいでしょう。ただし感情的になりやすい場合は後述のデメリットも踏まえる必要があります。
生活費の負担を抑えられる
別居をすると引っ越し費用や新居の家賃など追加の出費が生じますが、同居を続けていればそうした経済的負担を避けられます。
特に専業主婦の方や収入に不安がある方にとって、離婚成立までは一つの家計でやりくりできる安心感は大きいでしょう。別居後は夫が十分な生活費(婚姻費用)を払ってくれる保証もありません。
同居のうちに金銭面を含む離婚条件を取り決めてから離婚すれば、経済的不安を大きく軽減できます。
子どもの生活環境への影響が少ない
離婚前に無理に別居すると、子どもが転校や転園を余儀なくされたり生活環境がガラッと変わってしまう場合があります。同居を維持していれば子どもはこれまで通り同じ環境で生活でき、心理的負担を軽減できます。
少なくとも離婚が成立するまでは転校の必要もないため、子どもの生活リズムを急激に乱さずに済む点はメリットです。離婚後にどちらかが家を出るタイミングも自由に選択しやすくなります。
離婚の証拠や情報を集めやすい
同居中であれば、配偶者の不貞(浮気)の証拠や資産に関する資料を手に入れやすいという利点もあります。たとえば夫のスマホのメール・LINE内容、不倫相手との写真、預金通帳や保険証券の書類など、同居中の方が目にする機会が多く証拠集めが容易です 。
ただしこの点は相手方も同様で、お互いにプライバシーがない状態とも言えます。証拠集めをする際は見つからないよう注意するとともに、自分の大事な書類(預貯金通帳やハンコなど)は相手に勝手に見られたり持ち出されたりしないよう管理しましょう。
同居を続けるデメリット
一方、同居したまま離婚手続きを進めることには、以下のようなデメリットやリスクもあります。
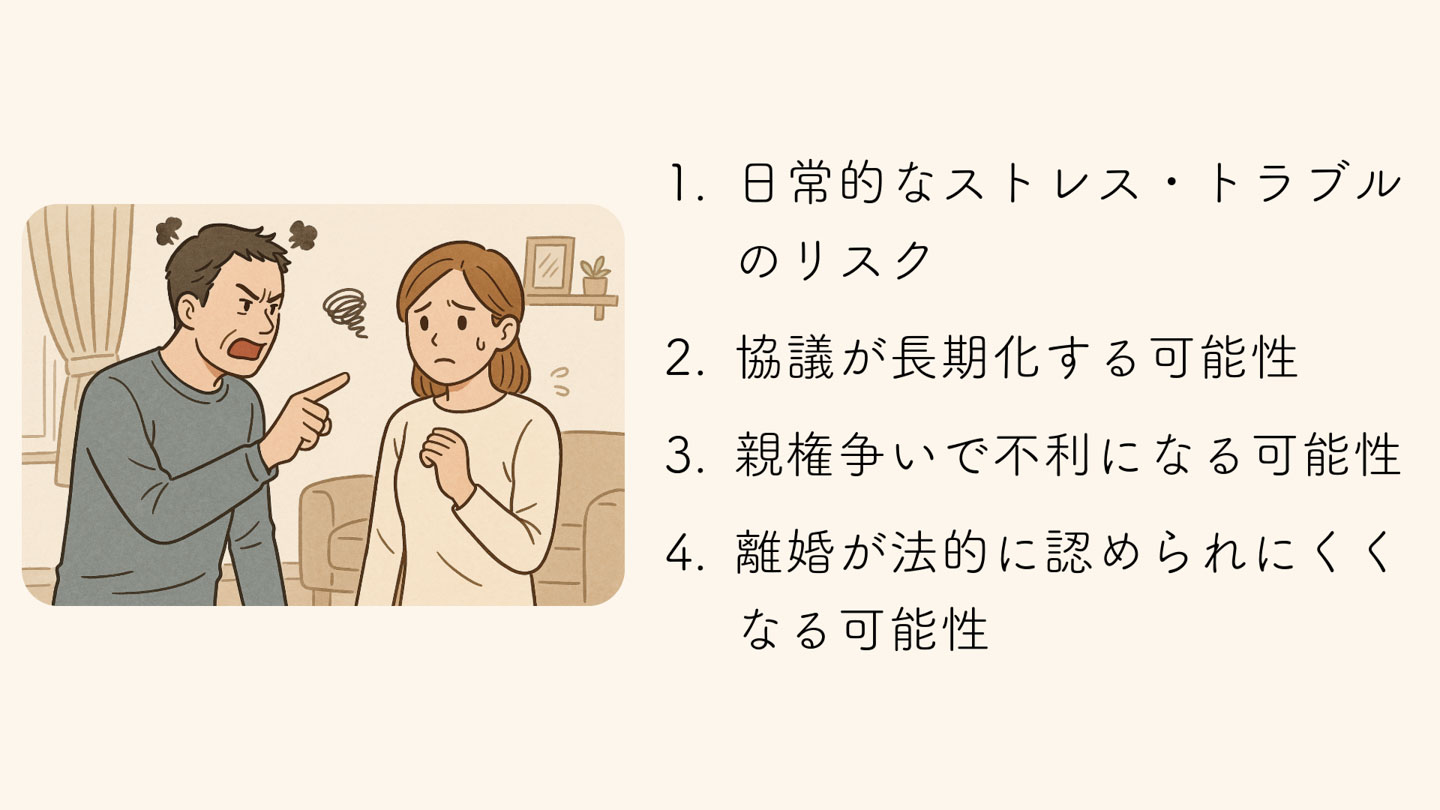
日常的なストレス・トラブルのリスク
離婚でもめている相手と毎日同じ屋根の下で顔を合わせ続けるのは、大きな精神的ストレスです。
相手と言葉を交わすたびに口論になったり、気まずい雰囲気で生活しなければならなかったりと、心の負担は想像以上に大きいでしょう。
また、夫婦関係が険悪な中で同居を続けると口論がエスカレートして暴言・暴力(DV)に発展する恐れもあります。
もともとDV被害がある場合には離婚話を切り出すことで身の危険が増すケースも報告されています。こうした深刻な事態が考えられる場合は無理に同居を続けず、身の安全を優先して別居や行政機関への相談を検討すべきです。
協議が長期化する可能性
同居中はいつでも話し合いができる反面、「いつでもできるから」と逆に離婚協議を先延ばしにしがちです。顔を合わせるたび感情的になってしまい話し合いを敬遠するあまり、気づけば1年以上も平行線のままだったというケースも珍しくありません。
別居していればお互い腹をくくって話し合いの場に臨むところ、同居だとダラダラと結論が出ない危険があります。
また、同居を続けることで相手が「このまま離婚しなくても生活できる」と安心し、離婚に真剣に向き合わなくなる可能性もあります。早期解決のためにはメリハリをつけて協議を行う工夫が必要です。
親権争いで不利になる可能性
お子さんがいる場合、離婚後の親権(どちらが子の親権者になるか)は大きな争点です。一般的に家庭裁判所では、現在子どもと一緒に暮らしている親の方を親権者に指定する傾向があります。
これは子どもの生活環境を大きく変えないように配慮する「現状維持の原則」によるものです。したがって、もし離婚協議が決裂して親権争いが生じた場合、事前に別居して自分が子どもを監護している実績を作っておいた方が有利に働くことが多いです。
逆に同居を続けている間はどちらが主に子どもの面倒を見ているか曖昧になりがちで、親権者を決める段階になって不利になる恐れがあります。※もっとも、離婚の話し合い中に一方的に子どもを連れ去るような行為は違法になる可能性もあるため注意が必要です。
離婚が法的に認められにくくなる可能性
相手が離婚に同意していれば問題ありませんが、もし夫が離婚を拒否して裁判にもつれ込んだ場合、同居を続けていること自体がハンデになるケースがあります。法律上、裁判で強制的に離婚が認められるには定められた離婚原因(有責行為や長期間の別居など)の立証が必要です。
夫婦がまだ一緒に暮らしている状態だと、「日常的に会話もあるし夫婦関係は破綻していない」とみなされ、離婚原因が認められにくくなる傾向があります。
反対に物理的に別居していれば、3〜5年程度別居が続いた時点で「婚姻関係は破綻した」と判断され離婚が認められやすくなるという実務上の目安があります。
明確な有責事由(不貞や暴力など)を証明できない場合、同居のままでは裁判離婚で不利になることが多い点に注意が必要です。
同居中でもできる離婚手続きの流れ
上記のメリット・デメリットを踏まえ、「別居せずに離婚手続きを進めるには具体的に何をすればよいのか」を確認しましょう。同居中でも可能な離婚手続きの流れとしては、以下のステップが一般的です。
家庭内別居で冷静に離婚準備を進める
まず、同居しているとはいえ夫婦関係が破綻しているのであれば、家の中で可能な限りお互い干渉し合わない状態(家庭内別居)に移行しましょう。家庭内別居とは形式上は同居していても実質的には別居と同じように生活することを指し、夫婦が同居しながら距離を置く方法です。
具体的には、寝室や食事の時間を分ける、会話は子どもの用事など必要最低限にとどめる、家事や財布も別々にするといった工夫をします。可能であれば「離婚に向けてお互い冷却期間を置こう」という形で合意の上、家庭内別居のルールを決めておくと良いでしょう。こうすることで余計な衝突を避け、離婚の準備に専念しやすくなります。
離婚の準備としてまず大切なのは、証拠や資料の収集と今後の生活設計です。同居中の今だからこそ入手しやすい資料も多いため、離婚を切り出す前に以下のような情報を集めておきましょう。
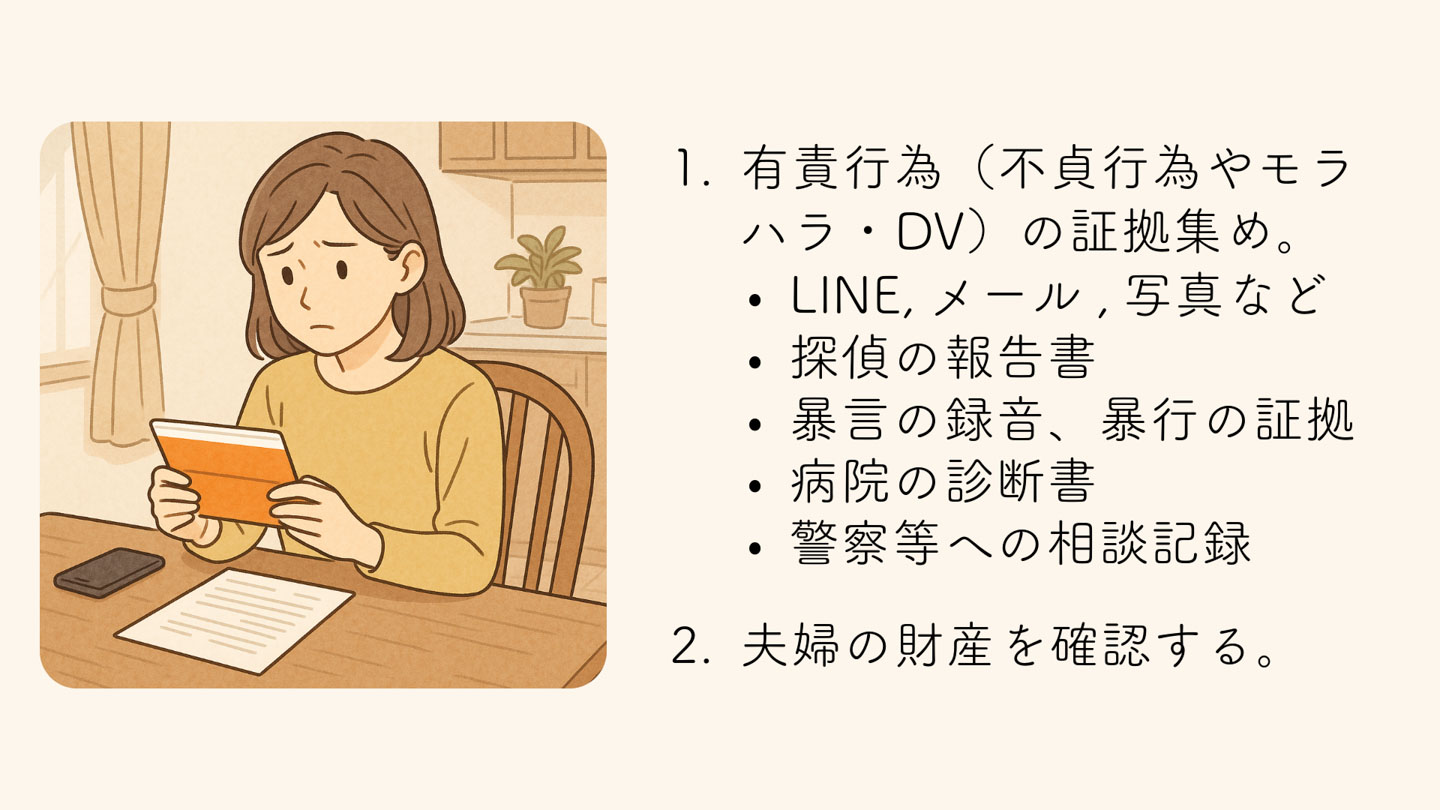
夫に離婚原因(有責行為)がある場合の証拠
夫の不貞行為の証拠(メール・LINE・写真、探偵の報告書等)や、モラハラ・DVの証拠(暴言の録音、暴力の診断書・写真、警察への相談記録等)。これらは離婚調停や裁判になった際にこちらの主張を裏付け、有利に進める材料になります。
夫婦の財産に関する資料
預貯金通帳の残高や入出金履歴、クレジットカードの明細、生命保険の証券、住宅ローンや不動産の権利証、給与明細や確定申告書など、夫婦の財産状況が分かるものをコピーして確保しておきます。
別居してしまうと相手の許可なく家に立ち入ることはできず、こうした書類を入手するのが難しくなるため、別居前の段階でできる限り集めておきましょう。財産分与でもめないための備えとして重要です。
離婚後の生活設計
離婚後に自分と子どもが生活していくプランも考えておきます。収入源の確保(仕事を続ける・始める、養育費の試算など)や、離婚後に住む場所の検討、実家の支援が得られるかどうか、といったポイントです。
現在同居中は住居費や生活費を夫が一部負担してくれている状況でも、離婚後は経済的に自立しなければなりません。
そのため離婚後を見据えた貯金計画や、公的支援制度の情報収集も進めておくと安心です。必要に応じて役所の相談窓口などでひとり親家庭の支援制度(児童扶養手当や公営住宅など)について調べておくのも良いでしょう。
このように準備を整えつつ、心構えとしては「感情的にならず冷静に進める」ことが大切です。家庭内別居中は相手と最低限の会話しか持たないようにすることで、怒りや悲しみを刺激される場面を減らせます。離婚に向けて着実にやるべきことを進めながら、タイミングを見計らって次のステップに移りましょう。
離婚協議(話し合い)で合意を目指す
離婚の準備ができたら、夫婦間で離婚協議(話し合い)を行い、できる限りお互い納得の上で合意することを目指します。日本の離婚の約90%は協議離婚(役所に離婚届を提出する形)といわれるほど、話し合いで解決するケースが大半です。まずは以下のようなポイントについて話し合いましょう。
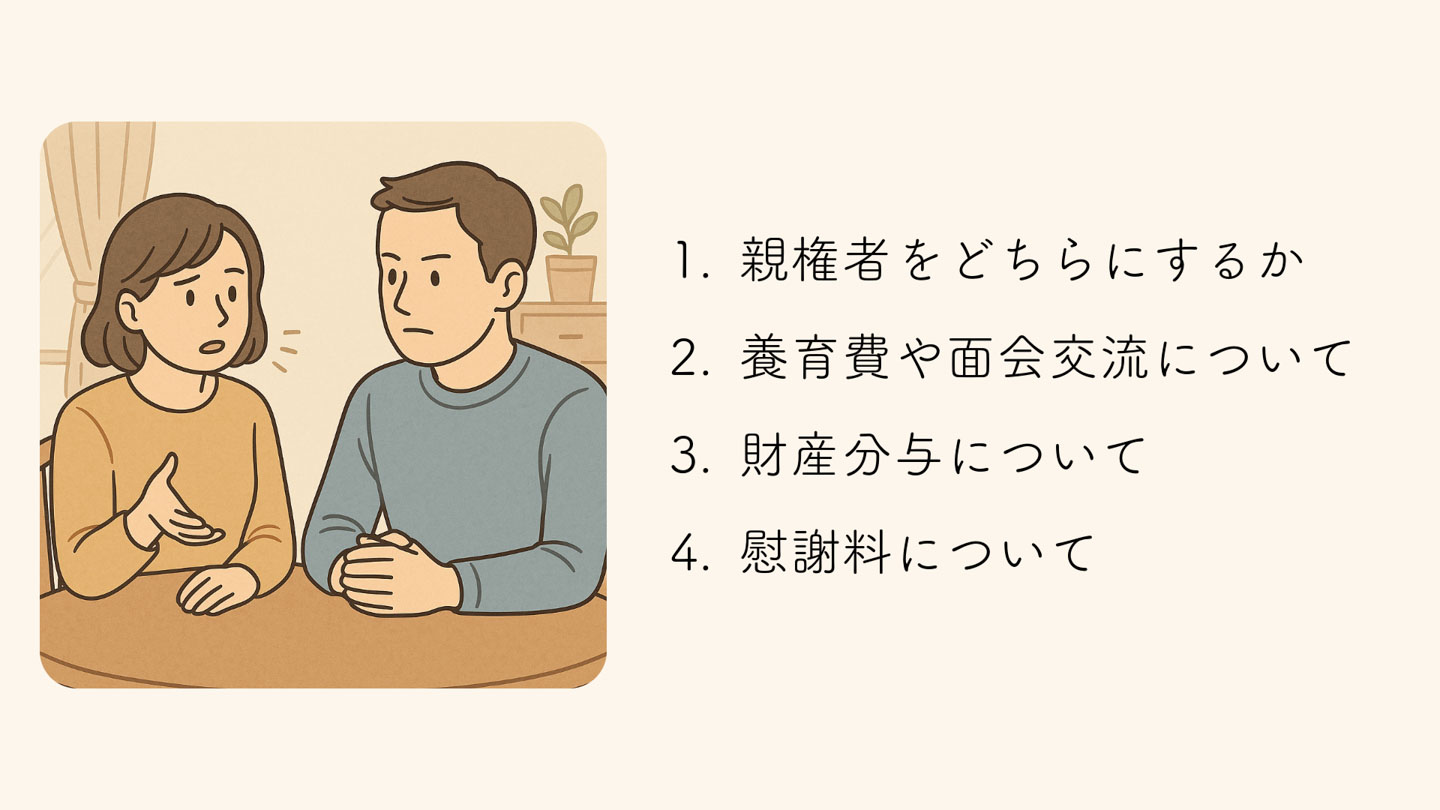
親権者をどちらにするか
お子さんがいる場合、離婚後は父母のどちらか一方を親権者に指定する必要があります(日本では離婚と同時に共同親権は認められず、必ずどちらか単独親権になります)。
一般的には主に子育てを担ってきた母親が親権者となるケースが多いですが、父親が強く希望する場合や母親の監護能力に問題がある場合などは争いになることもあります。子どもの福祉を最優先に考え、夫婦できちんと話し合って決めましょう。
養育費や面会交流
子どもを引き取らない側の親が支払う養育費の額・支払い方法、離婚後の面会交流(別居親と子が会う頻度や方法)について取り決めます。
養育費は公的な算定表を参考に子どもの年齢や人数、両親の収入に応じた適正額を算出できます。子どもの心情の安定のため、離婚後も定期的にもう一方の親と交流できるよう面会日程なども決めておくと良いでしょう。
財産分与
夫婦で築いた財産の清算として、現預金や不動産、車、保険、退職金などをどう分けるか決めます(詳細は後述「財産分与と生活費の取り決め方」を参照)。
通常は結婚後に形成した財産について半分ずつ分けるのが原則です。住宅ローンなど借金があればそれも含めて話し合います。トラブル防止のため、資産目録を作成して双方が内容を把握した上で合意することが大切です。
慰謝料
配偶者の不倫・浮気やDVなど、離婚原因について一方に明確な非(過失)がある場合、精神的苦痛に対する賠償金(慰謝料)の支払いについても決めます。
慰謝料は必ず発生するものではなく、あくまで法律上請求できるケースがあるという位置づけです。該当しない場合は慰謝料無しで離婚する形になります。該当しそうな場合は弁護士に相場や請求方法を相談するとよいでしょう。
上記のような項目でおおむね合意できれば、離婚協議書(離婚の合意内容を書面化した契約書)を作成することをおすすめします。
さらに公証役場で公正証書にしておけば、養育費の未払い時に強制執行できるなど強い効力を持たせることも可能です。最終的に市区町村役場に離婚届を提出すれば離婚は成立となります。
もし夫婦だけの話し合いで合意するのが難しい場合、第三者として弁護士に交渉を依頼する方法も検討してください。同居中であっても、弁護士が間に入ることで円滑に話し合いが進むケースは多々あります。
弁護士に依頼したからといって必ず別居しなければならないわけではなく、同居のまま代理人を立てて交渉することも可能です。その際、自宅では直接夫婦間で離婚の話をしないようにしましょう。弁護士を通じて回答すると決めておけば、家で言い争いになる事態を避けられます。
同居中の協議はただでさえ感情的になりやすいので、必要に応じて専門家の力も借りながら冷静に合意形成を図ることが大切です。
合意できない場合は離婚調停・裁判を検討する

夫婦間の話し合いだけではどうしても折り合いがつかない場合、あるいは相手が協議に応じない場合には、家庭裁判所での離婚調停を利用しましょう。離婚調停は法律上、裁判より前にまず話し合いで解決を試みるための手続きです(調停前置主義)。
夫婦どちらか一方が相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に調停を申し立てれば手続きが開始します。同居中であっても離婚調停を行うことは可能であり、実際に同居したまま調停に臨む夫婦もいます。
調停では調停委員(男女一人ずつの民間人ボランティア)が仲介役となり、夫婦それぞれから交互に話を聞いてくれます(夫婦が直接顔を合わせて話す場ではないのでご安心ください)。同居中は家で向き合うと感情的になって話し合えなかった夫婦でも、調停ではお互い別々の部屋に入って順番に調停委員と対話する形式のため、落ち着いて主張しやすくなります。
調停委員は中立的な立場で双方の言い分を聞き、合意点を探る手助けをしてくれます。同居によるストレスで当事者同士の話し合いが難しい場合でも、調停を活用することで歩み寄りの糸口が見つかることも多いです 。
離婚調停を申し立てると、裁判所から相手方宛てに調停期日の呼出状(通知書)が郵送されます。 同居中の場合、自宅にその郵便物が届くため配偶者も調停の申立てがあったことを知ります。
唐突に届くと相手が驚くかもしれませんので、可能であれば事前に「調停を申し立てるつもり」であることを伝えておく方が良いでしょう(DV等で難しい場合は無理せず)。
調停期日には夫婦それぞれ別々に裁判所へ出頭し、通常月1回程度のペースで話し合いが行われます。調停でまとまった離婚条件は調停調書という公的な合意文書にまとめられ、調書に従って離婚届を提出すれば離婚成立です。
調停でも合意に至らなかった場合、最終手段として離婚裁判(離婚訴訟)に進むことになります。裁判ではお互い弁護士を立てて法廷で争うことになり、調停以上に対立が深まってしまいます。
特に裁判では親権や財産分与、慰謝料などあらゆる点で自分に有利になるよう主張し合う必要があるため、同じ家に住み続ける精神的負担は非常に大きくなるでしょう。離婚裁判はあくまで「相手の同意がなくても離婚を認めてもらうため」の手続きですから、法律で定められた離婚原因(不貞行為・悪意の遺棄・3年以上の生死不明・強度の精神病・その他婚姻を継続し難い重大な事由)を原告側が立証しなければなりません。
裏を返せば、裁判まで進むケースは浮気やDVなど明確な原因があるか、長期間別居が続いているか、もしくは親権や高額なお金の問題で徹底抗戦となっているケースに限られます 。
同居したまま裁判に臨むのは現実的に非常に辛い状況ですので、調停が不成立になった段階で別居に踏み切ることも視野に入れましょう。裁判では弁護士による法的主張・立証活動が不可欠ですから、この段階では必ず弁護士に依頼することを強くおすすめします。
子どもへの影響と財産分与・金銭面の注意点
同居中に離婚を進めるにあたり、特に気を配るべきなのがお子さんへの影響とお金(財産分与や生活費)の問題です。それぞれ注意すべきポイントを見ていきましょう。

子どもの心のケアと親権の考慮
子どもの精神的ケアは最優先事項です。
同居しているとはいえ夫婦仲が冷え込んでいる状況は、子どもにとって敏感に感じ取るものです。両親が言い争ってばかりいると、子どもは「自分のせいでケンカしているのでは」と不安になったり、家庭に居場所がないように感じて心を痛めることがあります。離婚の話し合いを子どもの前でするのは避け、可能な限り普段通りの生活リズムや雰囲気を保つよう努めましょう。
離婚について子どもに伝えるタイミングも悩ましいところです。
年齢にもよりますが、ある程度物事が理解できる年齢であれば、最終的に離婚が決まった段階で両親揃って子どもにきちんと説明するのが理想です。「お父さんとお母さんは別々に暮らすけれど、あなたのことを愛している気持ちに変わりはない」ということを繰り返し伝え、決して子どもの責任ではないと安心させてあげてください。
突然片方の親がいなくなると子どもは大きなショックを受けますので、前もって伝える配慮が必要です。離婚後の生活(どちらと暮らし、もう一方の親とはいつ会えるのか等)についても具体的に話し、見通しを持たせてあげると子どもの不安は和らぎます。
親権の考慮については、先ほどデメリットの項目でも触れた通り、離婚後にお子さんをどちらが引き取るかという重要な問題があります。
協議離婚であれば夫婦の話し合いで決められますが、調停や裁判になった場合は最終的に裁判所が子どもの福祉の観点から親権者を判断します。
一般的には日頃の主たる養育者である母親が有利と言われますが、それだけで決まるわけではありません。
子どもの年齢・意思、現在の生活環境、兄弟関係、両親それぞれの養育環境(収入や住居、協力者の有無)など様々な要素が考慮されます。
同居中の場合、離婚成立までは両親とも子どもの世話をしている状態ですから、親権について話し合う際には「子どもの幸せにはどちらと暮らす方が良いか」という視点で冷静に考える必要があります。
もしお子さんがまだ小さい場合は母親が引き取った方が生活の面倒を見やすいかもしれませんし、学齢期で父親になついている場合は父親と暮らす方が安定するかもしれません。お子さんの気持ちにも耳を傾けながら、ベストな選択を検討しましょう。
話し合いで決まらなければ前述のように調停や審判で第三者に判断してもらうことになりますが、裁判所も**「今現在子どもが生活している環境をなるべく維持する」**方向で考える傾向があります。
そのため、離婚協議中に別居して子どもを連れて行くかどうかは慎重に判断しなければなりません(状況によって有利にも不利にもなり得ます)。いずれにせよ子どもの心に寄り添い、負担を最小限に抑える形で離婚後の生活を整えてあげることが大切です。必要に応じてスクールカウンセラーや専門機関に相談し、子どもの心のケアにも目を配りましょう。
財産分与と生活費の取り決め方
離婚に際しては財産分与という形で夫婦の財産を清算する手続きが発生します。また、同居中・別居中・離婚後と、それぞれの段階で生活費の負担をどうするかも重要なポイントです。金銭面で損をしないよう、以下の点に注意しましょう。
まず財産分与についてです。財産分与とは、結婚してから離婚までの間に夫婦が協力して築いた財産を公平に分けることです。対象となるのは預貯金、住宅や車といった不動産・動産、有価証券、保険の解約返戻金、年金の一部など多岐にわたります。
一方、婚姻前から持っていた貯金や実家からの相続財産など「特有財産」(夫婦の共同財産ではないもの)は基本的に分与の対象にはなりません。財産分与の割合は原則2分の1ずつとするケースが多いですが、専業主婦で収入がなかった方でも家事や育児で貢献していれば半分の権利がありますので安心してください。
スムーズに財産分与するためには、現在の夫婦の財産をきちんと把握することが不可欠です。同居中の今のうちに通帳のコピーを取る、財産目録を作るなどして、漏れなく資産を洗い出しましょう。
前述した通り別居前に証拠集めをしておくことが大事です。特に夫が家計を管理している場合、離婚後に通帳を開示してもらえず貯金額が不明…といった事態にならないように注意が必要です。
また、住宅ローンやカードローン等の負債もリストアップし、どちらが返済を負うのか決めておきます。話し合いで合意できればベストですが、難しい場合は調停で資料開示を求めることもできます。
生活費の取り決めについては、まず離婚が成立するまで(同居中・別居中)の期間と、離婚成立後の期間とで分けて考えます。
同居中の生活費
同居を続けている間は基本的にこれまで通り夫婦共同で生活費を支出する形になります。ただし家庭内別居状態で財布を分けている場合、食費や光熱費など細かい費用負担をどうするか取り決めが必要です。
「夫が住宅費と子どもの学費を負担し、妻が食費と光熱費を負担する」など役割分担を決めておくと良いでしょう。曖昧なままだと後々「誰がどれだけ出したか」で揉める原因になります。
なお、同居中でも夫が生活費を一切渡してくれないような場合には、法的には「婚姻費用分担請求」という手続きで家庭裁判所から生活費の支払いを命じてもらうことも可能です。
婚姻費用(こんいんひよう)とは夫婦が婚姻継続中に共同で負担すべき生活費のことで、別居中でなくとも請求自体はできます。実務上は住居費など同居特有の事情で算定が難しい面もありますが、困ったときは一人で抱え込まず専門家に相談してください。
別居中の生活費(婚姻費用)
別居に踏み切った場合、離婚が成立するまでの期間については「婚姻費用」の分担を取り決めます。一般的には収入の多い方から少ない方へ、夫婦と子どもの生活維持に必要な費用を支払う形になります。
家庭裁判所の算定表でおおよその金額の目安が示されていますので、話し合いではそれを参考に決めると良いでしょう。調停を申し立てれば裁判所で適正額を算定・勧告してもらえます。
離婚後の生活費
離婚が成立した後は夫婦ではなくなるため、「婚姻費用」の支払い義務は消滅します。その代わり、お子さんがいる場合は非監護親(子どもと暮らさない親)に養育費の支払い義務が生じます。
養育費は子どもの衣食住や教育にかかる費用を分担するもので、子どもが社会人になる(成人または高校卒業が目安)まで毎月支払うのが一般的です。金額は先述の算定表を基に決め、離婚協議書や調停調書に明記しておきましょう。
養育費以外にも、離婚後シングルマザー(あるいはシングルファザー)としてやっていくために利用できる公的手当・減免制度がありますので、役所で確認してみてください。
例えば児童手当やひとり親家庭の医療費助成、母子家庭等が利用できるローン(母子父子寡婦福祉資金貸付金)など様々な支援があります。離婚後の生活設計を立て、金銭面の不安をできるだけ取り除いておくことが大切です。
離婚の悩みは弁護士へ相談を
ここまで、同居したまま離婚する場合の進め方や注意点を解説してきました。
しかし、実際に離婚協議を進めるとなると「この条件で合意して大丈夫かな?」「調停を申し立てたいけど書類の書き方が分からない」など、悩みや不安が尽きないかもしれません。
離婚問題に直面したとき、一人で抱え込まず専門家である弁護士に相談することを強くおすすめします。

お電話・相談フォーム・LINEでのお問い合わせは24時間受付中!
東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に対応中!
平日18:00〜翌9:00及び休祝日での電話でのお問合せにつきましては、
受付内容の確認後、担当者より折り返しのご連絡をさせて頂いき予約を確定いたします。
最後に、弁護士に相談・依頼するメリットと、当事務所(弁護士法人グレイス)の無料法律相談の利用方法についてご説明します。
弁護士に相談するメリット
離婚問題を弁護士に相談・依頼するメリットには次のようなものがあります。
法律のプロによる的確なアドバイス
離婚にまつわる法律(親権や養育費、財産分与の権利義務、慰謝料請求の可否など)について専門家から正確な説明が得られます。インターネット上の情報だけでは判断が難しい細かな点も、あなたの事情に即してアドバイスしてもらえるので安心です。法的に有利な離婚条件や進め方を知ることで、誤った対応を避けることができます。
交渉や手続きの代行で精神的負担を軽減できる
弁護士に依頼すれば、相手方との話し合いや調停・裁判の手続きを代理人として進めてもらえます。直接顔を合わせて交渉するストレスから解放され、冷静に離婚問題に向き合えるでしょう。
特に同居中の場合、自分たちだけでは感情的になって話し合えないケースも多いですが、弁護士を通じて交渉すれば驚くほどスムーズに進むこともあります。
日常生活でのいざこざを回避し、プロの目線で公正な条件を引き出してもらえる点は大きなメリットです。
有利に離婚を進められる可能性が高まる
法律の専門家のサポートがあることで、結果的に自分に有利な条件で離婚を成立させられる可能性が高まります。例えば、適正な養育費・財産分与の金額算定、親権獲得のための主張立証、慰謝料請求すべき場合の手続きなど、素人では見落としがちなポイントもしっかりカバーしてもらえます。
弁護士のサポートがあれば安心して離婚手続きを進められますし、万一調停や裁判になっても心強い味方となるでしょう。
心の支えになる
長期間にわたる離婚協議や調停は、精神的に消耗するものです。弁護士に相談しておけば、困ったときにすぐ頼れる専門家がいるという安心感が得られます。
誰にも相談できず孤独な状態で悩み続けるより、第三者に話を聞いてもらうだけでも気持ちが軽くなるでしょう。法律相談は守秘義務がありますから、プライバシーが外部に漏れる心配もありません。
このように、弁護士に相談・依頼することで離婚問題の解決への道筋が見えてきます。当事務所でも同居したまま離婚を進めたいというご相談を受けることがありますが、弁護士のサポートによって有利に離婚を進められたケースが多数あります。悩みを一人で抱え込む必要はありませんので、まずはお気軽に専門家へご相談ください。
無料法律相談の予約方法と内容
弁護士法人グレイスでは、離婚に関する初回のご相談は60分まで無料で承っております。
無料相談をご利用いただくことで、費用の心配をせずに専門家のアドバイスを受けられます。相談のご予約は予約制となっており、以下のいずれかの方法でお申し込みいただけます。
メールフォームで予約
当事務所の公式サイトのお問い合わせフォームから、必要事項(お名前・ご連絡先・相談内容の概要など)を送信してください。担当者より折り返し日程調整のご連絡をいたします。
電話で予約
フリーダイヤル(※当事務所の電話番号)にお電話ください。24時間体制で受付スタッフが対応しております。営業時間外の場合でも仮受付を行い、後ほど担当者がご連絡して予約を確定いたします。「ホームページを見て離婚の無料相談を予約したい」とお伝えいただければスムーズです。
LINEで予約
当事務所公式LINEアカウントからも相談予約が可能です。LINEで友だち追加後、相談予約フォームよりご入力をお願いいたします。LINEではチャットボットを導入しておりお悩みに対する自動回答も実施中です。
実際の法律相談では、弁護士が現在の状況やお悩みを丁寧にヒアリングいたします。同居中で離婚を考えている経緯や、これまでの夫婦間の出来事、子どものことや経済状況など、安心してお話しください。相談内容に応じて、想定される解決策や手続きの流れ、見通しについて具体的にアドバイスいたします。
「この場合、親権はどちらになりそうか」「別居せず進めるリスクはあるか」「財産分与で注意すべきことは?」など疑問点は遠慮なくご質問ください。弁護士が法律的な観点から分かりやすくお答えし、今後何をすべきか明確にいたします。
もちろん相談したからといって必ず依頼しなければならないわけではありません。内容を聞いた上で「まずは自分で話し合ってみる」「調停になったら依頼を検討する」といった判断でも大丈夫です。無理な勧誘等は一切ございませんのでご安心ください。
無料相談を通じて、今まで漠然と不安だったことが整理され、「まずはこう動けばいいんだ」と道筋が見えてくるはずです。専門家の意見を聞くことで今後の方針に自信が持て、心の負担も軽くなるでしょう。
当事務所では離婚問題に精通した弁護士が親身になってご相談を承ります。お一人で悩まず、ぜひ一度無料法律相談をご活用ください。
別居できない事情があっても、離婚をあきらめる必要はありません。 本記事で解説したように、同居したままでも適切な準備と手続きを踏めば離婚は十分可能です。大切なのは、子どものケアと自身の安全・生活を確保しつつ、冷静に話し合いを進めることです。そのためにも専門家の力を借りながら進めるのが近道と言えます。
離婚に向けた一歩を踏み出そうとするあなたを、弁護士法人グレイスは全力でサポートいたします。初回60分の無料相談をご用意しておりますので、どうぞお気軽にご予約ください。
私たちと一緒に、より良い未来への一歩を踏み出しましょう。

お電話・相談フォーム・LINEでのお問い合わせは24時間受付中!
東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に対応中!
平日18:00〜翌9:00及び休祝日での電話でのお問合せにつきましては、
受付内容の確認後、担当者より折り返しのご連絡をさせて頂いき予約を確定いたします。

